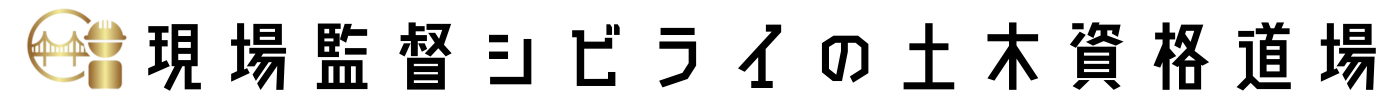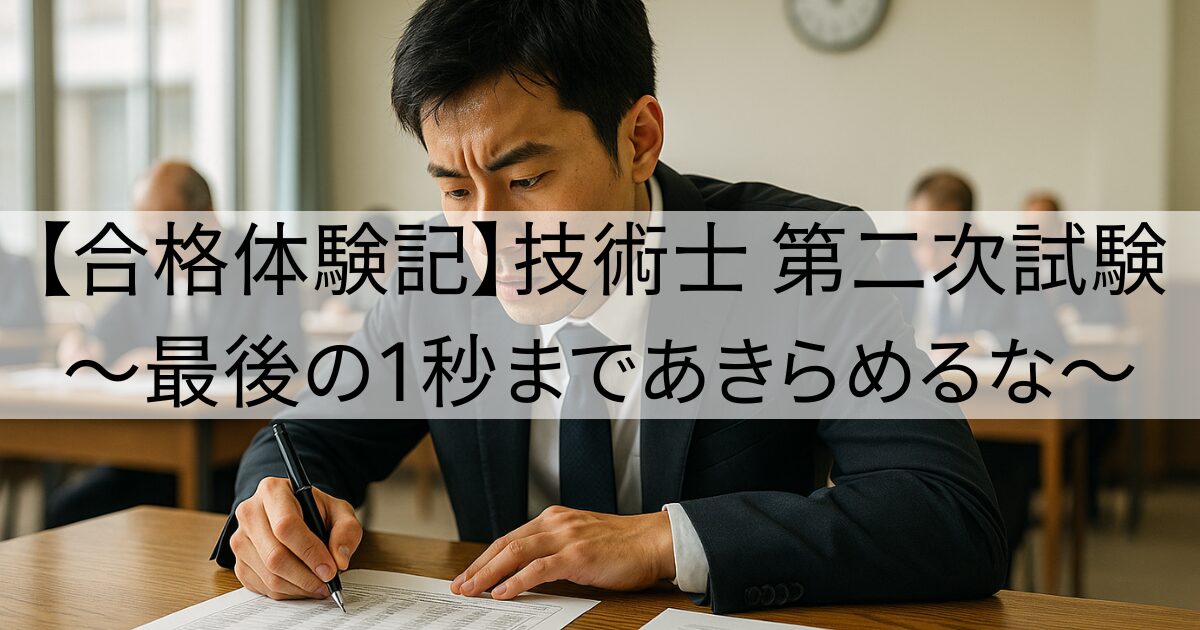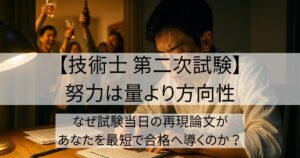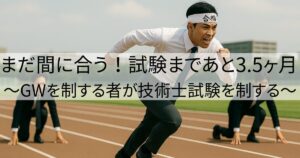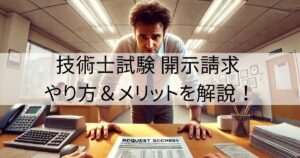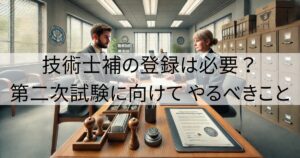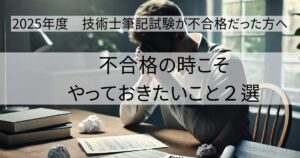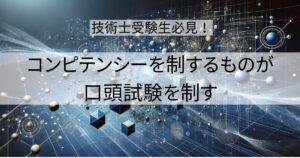はじめに
いよいよ明日から、技術士第二次試験(筆記試験)が始まりますね。
このブログを読んでくださっているあなたも、今、緊張と不安の入り混じった気持ちで、明日もしくは明後日を迎えようとしていることと思います。
どれだけ万全に準備をしてきたつもりでも、試験本番では思い通りに進まないものです。
時間配分をシミュレーションしていたはずなのに、実際の試験では思考に迷いが生じたり、設問の意図を慎重に読み取ろうとしたりする中で、気づけば時間が足りなくなっている。
技術士試験は、そうした“予定外”が当たり前のように起こる試験です。
それでも、決してあきらめてはいけません。
時間が足りなくても、頭が真っ白になっても、手を止めずに粘り続けたその先にこそ、合格への道が開ける瞬間があります。
私自身、試験中に「もう無理だ」と思った瞬間がありましたが、最後の最後までもがいた結果、なんとか合格をつかみ取ることができました。
この記事では、私自身が技術士試験に挑んだ日【2023年度 建設-施工計画、施工設備及び積算】の体験をもとに、「最後まであきらめない」ことの大切さをお届けできればと思います。
【午前】必須問題の安定した立ち上がり
<試験当日 午前の時間配分>
【必須問題】10:00-12:00
① 骨子作成 :10:00〜10:30(30分間)
② 1枚目作成:10:30〜11:10 (40分間)
③ 2枚目作成:11:10〜11:35 (25分間)
④ 3枚目作成:11:35〜11:55 (20分間)
⑤ 見直し&再現用メモ:11:55〜12:00(5分間)
出題内容は、「災害関連」と「インフラメンテナンス(第2フェーズ)」で、いずれも事前に準備していたテーマでした。
災害関連も対応可能でしたが、より確実に合格ラインを狙うため、国土交通省が令和4年12月に公表した「地域インフラ群再生戦略マネジメント」の内容を活かせるインフラメンテナンス(第2フェーズ)を選択しました。
骨子作成段階で記載内容はほぼ固まっており、文字数の調整を行いながら答案を作成しました。
試験時間中のタイムマネジメントはおおむね計画通り進み、5分ほど余裕を残して見直しと再現用メモを作成することができました。
午前の部は、ある程度の自信と余裕をもって終えることができたのです。
【午後】選択問題で直面した予想外の試練
<試験当日 午後の時間配分>
【選択問題】13:00-16:30
① 選択III 骨子作成 :13:00〜13:35(35分間)
② 選択III 3枚答案作成:13:35〜15:30 (115分間)
③ 選択II-2 骨子作成なし
④ 選択II-2 2枚答案作成:15:30〜16:10(40分間)
⑤ 選択II-1 骨子作成なし
⑥ 選択II-1 1枚答案作成:16:10〜16:30(20分間)
⑦ 見直し できず
試験開始合図の直後、まずは全選択問題に目を通しました。
選択II-1については、コンクリートに絞って準備していましたが、出題内容は予想外の「高強度コンクリート」でした。品質関連や劣化機構の全般、その他の特殊コンクリート(暑中コンや寒中コン、プレキャストや高流動など)については対策していましたが、高強度については未準備だったため、最後に回すと判断しました。
選択II-2は、
設問(1)が過去問と類似した内容で、事前準備で対応可能と判断。
設問(2)は一見難しそうでしたが、少し時間を作ればコンクリートの品質管理に関する知識を活かせそうだと考えました。
設問(3)はトラブル発生時の具体的状況設定が新しく、少し動揺しましたが、実務経験を思い出しながら対応できると判断しました。
選択IIはいずれも少し考える時間が必要になりそうであり、先に手を付けると選択IIIの回答時間が作れなさそうであったため、後回しにした方が良さそうと判断しました。
慎重を期すべきは選択IIIでした。
昨年度は選択IIIがC寄りのB判定だったため、今回は確実に点を取りたいという思いがありました。
選択IIIについて、
「カーボンニュートラル」と「週休2日制」に関する出題でした。
カーボンニュートラル関連は最近の頻出テーマであったため、「施工計画、施工設備及び積算」の技術者としての回答を意識するために「施工時の低炭素化」は準備していました。
しかし今回の出題では、構造物の整備から供用後までを視野に入れた内容が求められる出題であり、準備していた内容では対応が難しく、回答の方向性を慎重に決める必要があると判断し、最初に取りかかることにしました。
慎重に骨子を整え、時間をかけて3枚の答案を完成。
その代償として、選択IIにかけられる時間は残り1時間、この時点で白紙の答案用紙が3枚残った状態でした。
【緊急判断】骨子作成を省略し、“1枚でも多く書く”作戦へ
白紙の答案用紙3枚を残し、残り1時間。
通常ペースでは1枚30分必要な私にとっては厳しい状況でした。
途中で消しゴムを使う数行の書き直しが生じた時点で、おそらく時間切れになってしまいます。
このとき私は、骨子作成を省き、設問ごとの目安行数をマークしつつ、直接答案用紙に書く方法に切り替えました。
「完成度」よりも「全設問を埋める」ことを優先し、書きたいことがあっても目安行数を超えないように調整。
回答の方向性だけは間違えないように、時間がない中でも問題文はしっかりと読みつつ、普段の現場業務と出題状況を照らし合わせながら、なんとか選択II-2を仕上げました。
【白紙の1枚】残り20分、頭の中は“真っ白”
その後、急いで選択II-1へ。
選択III,II-2で必死だったため、II-1の高強度コンクリートについて回答の準備がないことを忘れていました。
白紙の答案用紙1枚(600文字)を残し、試験時間 残り20分。
頭の中には書くネタ無し。
正直
「もう無理だ」
と思いました。
「ここで諦めて来年また受けるか。」
という考えが何度も頭をよぎりました。
でも、ふと思いました。
「選択II-1がC判定でも、他でカバーできていればワンチャンあるかも」
「まだ可能性が0になったわけではない」
「とにかく白紙は避けよう。まず1行だけでも書こう」
そうして手を動かし始めた瞬間――
【過去の努力が、今の自分を助ける】
手を動かし始めたその瞬間――
突然デジャブのような感覚になり、ノートのあるページが脳裏によみがえりました。
それは10ヶ月前、コンクリート主任技士試験に向けて整理した「高強度コンクリート」に関する1ページでした。
まったく見返していなかったはずのページが、まるで昨日読んだかのように、鮮明に蘇ったのです。
思い返せば、コンクリート主任技士の勉強では「エビングハウスの忘却曲線」を意識して長期記憶を狙った勉強方法を実践していました。
「試験のためだけの知識でなく、現場で使える知識にする」
そう思って積み重ねていた小さな復習が、この土壇場で、まさかの形で自分を救ってくれたのです。
まさに、
「昔の自分が今の自分を助けてくれた」
「点と点がつながった」
と強く感じた瞬間でした。
まとめ【最後の1秒まであきらめるな】
技術士試験は、予想外の事態の連続です。
想定外の出題、時間不足、動揺…。
でも、最後の1分1秒まで諦めなければ、思わぬ形で過去の努力が力を貸してくれることがあります。
白紙になりかけた答案を救ってくれたのは、「あの日」積み上げた知識でした。
今年受験される皆さん、
不安もあることと思います。自信が持てない問題に出会うかもしれません。
それでも、最後の1分1秒まであきらめず、自分を信じて挑んでください
技術士試験は、その場しのぎではなく、日々の積み重ねが問われる試験です。
これまでコツコツ積み重ねてきたあなたなら、過去の努力がきっと、今のあなたを支えてくれるはずです。
あなたが今まで積み重ねてきた努力は、決して裏切りません。
自分を信じて、最後の最後まで手を止めず、答案用紙を埋めきってください。
試験前の貴重な時間にも関わらず、最後まで読んでいただき、誠にありがとうございます。
試験直前は不安や焦りも大きい中で、こうして私の体験や言葉に目を通してくださったこと、とても嬉しく思います。
大切な挑戦に向けて、この記事が少しでもあなたの背中を押すことができたなら幸いです。
あなたの努力が実を結び、良い結果につながることを心から願っています。
「ここでの勉強が、あなたの未来を変える。」
【現場監督シビライの土木資格道場】では、あなたの努力が実を結ぶよう、これからも役立つ情報を発信し続けます。
資格取得というゴールは、その道のりにも大きな意味がある。
今日学んだことが、明日の成長につながり、その成長の積み重ねが、あなたの未来を変える。
また次の記事でお会いしましょう。あなたの挑戦を、全力で応援しています。
共に頑張っていきましょう!