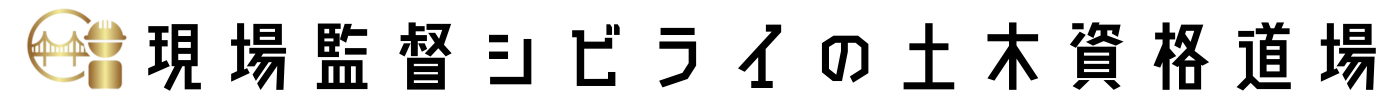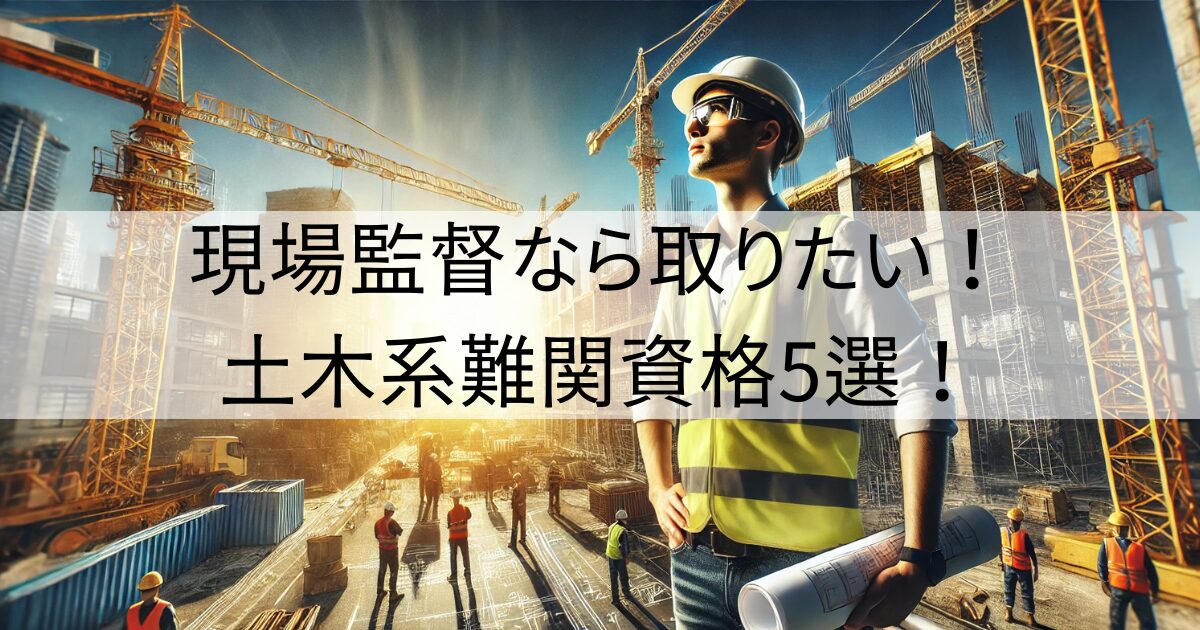はじめに
現場監督として活躍するなら、日々の勉強が欠かせません。そこでオススメなのが資格取得です!
特に難関資格を持っていることで、キャリアアップや転職の際に大きな武器となりますす。また資格取得の過程での学びが、業務に対する見方をも変えてくれることでしょう。
今回は、現場監督が取得を目指したい土木系の難関資格5つを紹介し、それぞれの難易度や施工管理業務への活かし方について、現役の現場監督である私自身の実体験に基づき解説します。
このサイトでは、より具体的でリアルな内容をお伝えするために、自分が実際に取得した資格についてしか書いておりません。
よくある、ネットで調べたことをまとめただけの薄い内容を、無責任に皆さんに向けて発信したくないからです。
そのため書いている内容(優先度や難易度なども)は、主観的で偏った内容となっているかもしれませんが、自分の実体験に基づく内容となっていますので、少しでも参考になれば嬉しいです。
現場監督なら取りたい!土木系難関資格5選!
1. 一級土木施工管理技士(優先度★★★★★、難易度★★☆☆☆)
資格の概要
一級土木施工管理技士は、土木工事の現場監督としての能力を証明する資格です。
土木工事の現場管理を行う上で必須ともいえる資格です。1級を取得すると、大規模な公共工事などの主任技術者・監理技術者として活躍できるようになります。
取得のメリット
- 監理技術者になれる(1級合格後に監理技術者講習を受講する必要あり)
- 昇進・昇給の可能性が高まる
- 建設業界での市場価値が向上する
会社としても、一級土木の所持者は新規の入札案件などに監理技術者としてノミネートさせることができるため、工事の受注チャンスが広がります。また土木施工管理技士がいることで、会社の経営事項審査(公共工事の入札に参加する際に受ける審査)の点数が加点されるなどのメリットもあるため、資格手当などを設定している会社も少なくないと思います。
試験の難易度
試験は学科試験(第1次検定)と実地試験(第2次検定)に分かれており、特に第2次検定の記述式問題がやや難関です。施工経験をしっかり整理し、論理的に記述する練習が必要です。難しいことを書く必要はなく、必要な情報を端的に表現することが合格のカギとなります。
施工管理業務への活かし方
- 大規模な公共工事やインフラ整備工事で主任技術者・監理技術者として活躍
- 施工計画の立案や品質管理業務の精度向上
- 若手技術者への指導や育成に貢献
現場監督として初めて現場に出た時は「あれもこれもやらなければ」と覚えることがいっぱいです。訳も分からず言われたことを消化する日々もたくさんあるでしょう。
仕事をする上で上司や先輩から言われた「しなければならないこと」を覚えていくことはもちろん大切ですが、一級土木の勉強では現場に関係する法律など施工管理について体系的に客観的に学びます。
その結果「なぜ、しなければいけないのか」という視点を持てるようになり、より意味を持った現場管理に繋げることができるようになるでしょう。
一級土木施工管理技士の取得は、工事担当者→土木技術者にステップアップするための大きな一歩となります。
【おすすめの参考書】私が実際に使用していた参考書
こちらは私が勉強の際に実際に使用していた参考書(の最新年度版)です。
参考書のレビューや具体的な勉強方法については、別記事でまとめたいと思います。
第1次検定
第2次検定
2. コンクリート技士 (優先度★★★★☆、難易度★★☆☆☆)
資格の概要
コンクリート技士は、コンクリートに関する基本知識と品質管理能力を有することを証明する資格です。コンクリート技士/主任技士は、コンクリートの製造や品質ということで、どちらかというと”生コン”に焦点を当てている資格になります。
コンクリート系資格(技士/主任技士、診断士)の中で、一番現場監督向けの資格といえばこの資格でしょう。
取得のメリット
- コンクリート工事の基本的な品質管理ができる
- コンクリートの施工計画や配合設計に活かせる
- 建設業界での信頼度向上
配属現場によっては、すぐにコンクリートに関わらない現場もあるかもしれませんが、土木工事に携わる上でコンクリートの知識は必須となってきます。
特に発注者とのコミュニケーション(雑談)の中でも、コンクリートについてかなり専門的な質問を受けることもあり、勉強していて良かったと感じる場面が多々ありました。
試験の難易度
試験は学科試験のみで、比較的取得しやすい資格ですが、コンクリートの材料特性や施工方法に関する知識が求められます。生コンクリートを現場で扱ったことのある人でも、現場経験だけで突破できる資格ではありません。配合設計や製造など、現場に来る前の生コンに関する知識も必要になってきます。
施工管理業務への活かし方
- コンクリート施工における品質管理業務に携われる
- 配合計画や強度管理の知識を活かし、適切な施工計画を立案
- 施工時のトラブル対応能力が向上
コンクリートの打設計画を行う上で、根拠を持った品質管理計画を考えられるようになります。生コン打設では、品質に関する色々なルールがありますが、それがコンクリートの品質にどのように影響するのかを理解できるようになります。
特にトラブル対応能力の向上については、変化を実感しやすいでしょう。
特にコンクリート打設中は、予想外のトラブルや迅速な判断を迫られる場面が多々出てきます。その時メカニズムなどに対する理解が深ければ、品質的な根拠を持って現場判断をすることができるでしょう。
上司からしても
「どうすれば良いですか?」
と判断を委ねてくる担当者よりも、
「〇〇な理由で××な状況ですが、△△な観点から品質面への影響はないので◻︎◻︎でいこうと思います。よろしいですか?」
と根拠を持った提案をしてくる部下の方が、担当にして良かったなと思われるはずです。
【おすすめの参考書】私が実際に使用していた参考書
こちらは私が勉強の際に実際に使用していた参考書(の最新年度版)です。
参考書のレビューや具体的な勉強方法については、別記事でまとめたいと思います。
コンクリート技士 試験問題と解説 →紙書籍で購入
コンクリート技士 合格テキスト&過去問 →電子書籍で購入
3. コンクリート主任技士(優先度★★★☆☆、難易度★★★☆☆)
資格の概要
コンクリート主任技士は、コンクリート技士の上位資格です。
コンクリートに関する高度な知識と技術を持ち、品質管理や施工管理を行う専門資格です。生コンプラントの品質管理責任者や工場長が持っているイメージがあります。
取得のメリット
- コンクリート工事における技術的な信頼度が向上
- 品質管理の責任者としての役割を果たせる
- 施工管理技士と併せ持つことで、キャリアの幅が広がる
様々な現象のメカニズムを知ることで、品質管理への理解が格段に深まります。
試験の難易度
試験範囲が広く、コンクリート材料や施工方法、耐久性評価など多岐にわたるため、体系的かつ深い理解が求められます。
コンクリート技士に比べ、難易度は格段に上がります。私はコンクリート技士受験直後(技士の過去問で90%以上取れる状態で自信満々のとき)に、主任技士の過去問にも挑戦しましたが、60%程の正答率だった記憶があります。それに加えて記述式問題も追加されるので、それなりの覚悟と対策が必要になります。
施工管理業務への活かし方
- コンクリート工事の品質管理責任者として活躍
- 高度な耐久性評価や劣化診断を実施できる
- トラブル発生時の適切な対策を立案できる
コンクリート技士に比べてより専門的な知識と理解が深まります。
コンクリート技士より優先度を低くしているのは、合格するためには現場で必要となる知識以上に、専門的な知識を頭に入れる必要があるためです。要するに、現場監督としてはややオーバースペックな印象かもしれません。
ダムなど大型コンクリートの現場であれば資格要件などに定められている場合もあるため、自身の工種によって必要性は変わってくるかと思います。
それなりの勉強時間と労力が必要になりますが、取得できればコンクリート技士の完全上位互換の位置付けになります。
【おすすめの参考書】私が実際に使用していた参考書
こちらは私が勉強の際に実際に使用していた参考書(の最新年度版)です。
参考書のレビューや具体的な勉強方法については、別記事でまとめたいと思います。
コンクリート主任技士 試験問題と解説 →択一式対策
キーワードを活用した小論文のつくり方 →記述式対策
4. コンクリート診断士 (優先度★★☆☆☆、難易度★★★☆☆)
資格の概要
コンクリート診断士は、既存のコンクリート構造物の劣化診断や補修・補強設計を行う専門資格です。「コンクリートの医者」とも言われる資格です。
コンクリート診断士は、コンクリートの診断ということで”既存のコンクリート構造物”に焦点を当てている資格になります。
コンクリート技士/主任技士とは全く系統が違います。
老朽化が進む社会インフラのメンテナンスが重要視される今、この資格の需要は非常に高まっています。
現場での施工管理だけでなく、インフラの長寿命化を考えた維持管理の視点も持てるようになります。
取得のメリット
- 老朽化したインフラの維持管理に貢献できる
- 施工管理だけでなく、診断・補修の分野にも携われる
- 高度な専門知識を持つことで、発注者からの信頼が高まる
コンクリート構造物のひび割れ調査や非破壊試験を行う際も、コンクリート診断士が行うことで客先からの信頼度は格段に上がります。
技士/主任技士では触れない分野(現場で触れない分野)についても学ぶことができます。現場での生コンの品質管理が将来的にどのように影響してくるかの具体的なイメージが持てるようになり、コンクリートに関する視野が広がります。
試験の難易度
問題が専門的で、診断に関する経験と知識が求められるため、実務経験をしっかり積んだ上での受験が推奨されます。ゼネコンで現場監督としての実務経験しか無い場合、ほとんどが初見の分野になってきます。化学系の計算や知識が多くなってくるため、より専門的な知識が必要になります。
また、主任技士に比べて記述式の配点が高い特徴があります。その分、記述力が求められるかと言えばそうでもありません。問われるテーマは違えど、論文の”型”と”書くべき内容”は決まっているからです。
”主任技士”と”診断士”ではどちらが難しいかという議論がありますが、ゼネコンの現場監督からすると主任技士の方が馴染みのある分野なので、勉強はしやすいです。主任技士は少しは知識の積み重ねがある状態からですが、診断士はほぼゼロからのスタートとなるでしょう。
逆に診断・維持管理・補修関係の実務経験が多い方からすると、診断士の方が勉強にとりかかりやすいかもしれません。
このように個人の実務経験内容によって難易度は変わると思いますが、試験範囲や深さ、過去問演習での対応可否などを考慮すると、客観的な難易度は”同等である”と思います。
施工管理業務への活かし方
- 既存構造物の劣化診断を実施し、適切な補修計画を策定
- 耐久性向上のための施工計画を立案
- 維持管理業務のプロフェッショナルとして活躍
現場の施工管理に直接活かせる部分は、それほどありません。会社で他の部署に行ったり、自身のキャリア選択をする上では重宝されるかもしれません。
【おすすめの参考書】私が実際に使用していた参考書
こちらは私が勉強の際に実際に使用していた参考書(の最新年度版)です。
参考書のレビューや具体的な勉強方法については、別記事でまとめたいと思います。
コンクリート診断士試験 キーワード130 →キーワード学習
コンクリート診断士試験 完全攻略問題集 →択一式対策メイン
コンクリート診断士試験 合格指南 →記述式対策メイン
キーワードを活用した小論文のつくり方 →記述式対策
5. 技術士(建設部門) (優先度★★★★☆、難易度★★★★★)
資格の概要
技術者の最高峰とも言われる国家資格です。
建設部門という1つの部門の中だけでも、専門科目が11つに分けられ、自身の業務経歴に応じた科目で受験することになります。
取得のメリット
- 国家資格の中でも権威が高く、評価が高い
- 独立やコンサルタント業務に有利
- 特に公共工事において発注者からの高い信頼を獲得できる
発注者(特に公共工事)において、信頼度が格段に高まります。
令和6年度技術士第二次試験統計.pdf(技術士会HPより)
技術士試験の統計データの「6.勤務先別・最終学歴別試験結果」を見ると”官庁”と”地方公共団体”の対受験者合格率が高い傾向にあります。
これは発注者側機関の方々が、きちんと試験対策をして試験に臨んでいる、つまり技術士資格の取得を重要視しているという表れでないでしょうか。
試験の難易度
一次試験(基礎知識)と二次試験(筆記・口頭試験)があり、特に二次試験は記述式で高度な専門知識が求められるため、十分な対策が必要です。
特に選択II-2では実際の業務に近いシチュエーションの問題が出ます。そのため、自身の業務経験にあった専門科目で受験することが大事です。
現場監督の場合、これまでの業務経歴で工種に大きな偏りが無ければ、「施工計画」での受験がオススメです。受験者数が1番多く、情報量も多いため勉強しやすいです。
私もそういったアドバイスをもらい、施工計画での受験を決めました。
施工管理業務への活かし方
- 技術的な協議、説明における説得力が高まる
- 大規模プロジェクトの計画立案に携われる
- 発注者からの高い信頼の獲得
- 公共工事の発注者側の立場として働くことも可能
【おすすめの参考書】私が実際に使用していた参考書
こちらは私が勉強の際に実際に使用していた参考書(の最新年度版)です。
参考書のレビューや具体的な勉強方法については、別記事でまとめたいと思います。
技術士 第二次試験 (建設部門) 最新キーワード100 →キーワード学習
技術士 第二次試験 (建設部門) 合格指南 →論文対策
まとめ
今回は「現場監督におすすめの土木系資格」について、私が実際に取得した資格をベースにまとめてみました。
※優先度や難易度については、私の実体験に基づく主観で評価していますので、あくまでも参考程度に見ていただければと思います。
現場監督におすすめの土木系難関資格
1. 一級土木施工管理技士(優先度★★★★★、難易度★★☆☆☆)
2. コンクリート技士 (優先度★★★★☆、難易度★★☆☆☆)
3. コンクリート主任技士(優先度★★★☆☆、難易度★★★☆☆)
4. コンクリート診断士 (優先度★★☆☆☆、難易度★★★☆☆)
5. 技術士(建設部門) (優先度★★★★☆、難易度★★★★★)
現場監督としてのキャリアを高めるためには、これらの資格の取得が有効です。一級土木施工管理技士をゴールとする方も多いですが、+αの資格勉強をすることで、より土木技術者としての専門性、スキルを高めることができます。
自身が所属する組織内だけでなく、建設業界での市場価値も高まり、今後のステップアップやキャリア形成にも繋がることでしょう。
ここまで読まれている方の中には、資格を取りたいが何から始めればいいか分からない、自分にも取れるのだろうか、と悩んでいる方も多いと思います。
“悩む”ということは、”取りたい”という思いがある証拠です。そもそも興味のないことは、頭の中を一瞬で通り過ぎていきます。”悩む”ことさえありません。
 シビライ
シビライその”取りたい”思いが少しでもあれば、なんとかなります。
まずは数年後にその資格を持っている自分をイメージをしましょう。
●”技術士”と記載された名刺を交換し、お客様がお〜という表情をしていますか?
●資格手当で給与がアップしたり、社内で昇級していますか?
●独立や転職で、新たなキャリアをスタートさせていますか?
どんなシーンでも構いません。
将来の自分が、当たり前のようにその資格を持っている具体的なシーンを想像するのです。
そのイメージはいつか必ず実現します。
実現させるために、ここからの行動を変えるのです。



もう〇〇歳だから?
明日になれば、また一日年を取ります。
あなたの残りの人生で一番若い日は、今日いまこの瞬間ですよ。
一歩踏み出したい、でも踏み出せない。
そんなあなたのために、私はこのサイトを開設しました。
このサイトのモットーは、資格に関するリアルな情報、合格体験談や試験攻略のノウハウ、勉強法やモチベーションの保ち方など、、私自身が資格勉強をしていく中で、”受験前に欲しかったけど手に入れられなかった情報”を発信していくことです。
このサイトが、あなたが一歩を踏み出すキッカケになれたら良いなと思っています。
「ここでの勉強が、あなたの未来を変える。」
【現場監督シビライの土木資格道場】では、あなたの努力が実を結ぶよう、これからも役立つ情報を発信し続けます。
資格取得というゴールは、その道のりにも大きな意味がある。
今日学んだことが、明日の成長につながり、その成長の積み重ねが、あなたの未来を変える。
また次の記事でお会いしましょう。あなたの挑戦を、全力で応援しています。
共に頑張っていきましょう!